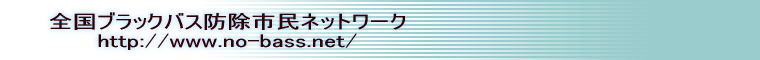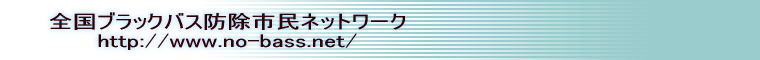●アカミミガメ、アメリカザリガニの処理方法
 細谷
細谷 今日のシンポジウムは大きく2部に分かれていました。午前の基調講演と、午後の「20年の具体的な活動と今後の課題」です。質問は2つしか届いていませんが、会場でも質問を受け、最後に私にまとめをさせていただければと思います。
まず、基調講演です。次の質問をいただいています。中島さんご回答お願いします。
「アカミミガメ、アメリカザリガニが手に入ってしまった場合、どう処理をするのがよいですか。市町村で引き取れるシステムが大切だと思います」。
中島(環境省) まず、自主処理される場合は、なるべく苦痛を与えない方法で処分していただければありがたいです。個人ではなかなかむずかしいと感じられるかもしれませんが、冷凍がよいと言われています。
また、拾得物であれば、警察に届けてもらうことが基本です。2023年に外来生物法が改正された際に、条件付特定外来生物が届けられた場合も犬や猫と同様に取り扱うことについて、警察庁から各都道府県の警察に対して通知されています。遺失者が判明しない場合の取り扱いについては、環境省から地方公共団体の環境部局に対し、通知を行っています。
細谷 ありがとうございます。次の質問です。
「ブラックバスなどは以前から違法放流が問題になっていますが、大人による組織的なものだけでなく、身近な場所で釣りをしたい子ども、特に中高生によるものもあると思います。学校教育で扱われていないためと思われますが、どういう展開が必要でしょうか」
中井さん、ご回答いただけますか。
中井(ルイ・パストゥール医学研究センター) 今、教育の現場は大変で、違法放流についての啓発まで行うのはむずかしいと思います。細谷さんも「外来生物問題についての啓発は教育委員会を通じて行ってはどうか」とお話しされました。
外来生物問題もいろいろあり、たとえばメダカは今観賞用品種がどんどん作られていますが、一方で学校での観察の対象にもなっています。学年が上がるとき、飼育していたメダカをどうするか。「命の教育」も謡われ、処分することもむずかしい。でも、処分してもらわないと、逃がされてどこのメダカかわからないものが地域個体群の遺伝的な特性を乱す可能性もあるという込み入った話もあります。そもそも外来生物法自体、今でもあまり知られていません。ですから、まず「銃や麻薬と同じくらいやばい」「きびしい罰則がかかる」と知ってもらうことだと思います。この周知はまだ不十分だと思います。
細谷 今日発表の法政大学のアンケート調査によれば、幼い頃、若い頃の動機づけがいかに大事か表れていたと思います。近畿大学でも、大学入学時、優秀なバサー(バス釣り人)がたくさん入ってきます。卒業するときは優秀な希少種保護論者に転換して卒業します。その辺は教育委員会、あるいは教員の腕の見せどころでもあると考えています。
●いなくなってどのくらいで「完全駆除」できるか?
 参加者
参加者 外来生物を駆除してどれくらいたてば完全駆除と言えるかということですが、アルゼンチンアリでは捕獲ゼロになってから、だいたい40か月という基準が示されました。水生生物の場合、その基準で大丈夫でしょうか。
藤本泰文(宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団) その期間は発見率などから算出すると思いますが、個々の生きもので違うと思います。水生生物は発見率が非常にきびしいので、期間を長くとる必要があると思います。また、伊豆沼の場合、外から入ってくる(注/再放流される)数を考えると、もっときびしいと思います。
五箇さんはまずモデルを出され、それに現実がどうついてくるかを見ていこうということではないかと思います。
細谷 ありがとうございます。藤本さんの現実的なデータは、特定外来生物を完全に駆除しても、その後の変化に私たちの思いが至っていないことを示していると思います。藤本さんにはこれをリバウンドとしてご指摘いただきました。ほかにも、たとえば皇居のお濠からブラックバスがいなくなったら、ウシガエルだらけになった事例もありました。私たちは一生懸命駆除しますが、そのあと想定外のことが起こり、生態系の回復はシミュレーションがしにくい。これをメソプレデター(中間捕食者)・エフェクトと言います。
中井 補足です。(五箇さんが紹介した)アルゼンチンアリは、駆除のための手法と、いるいないのモニタリングの手法がほぼ同じ、という特殊性があります。つまり、とれる数がどんどん減っていく経過が一つのデータセットになり、分析がしやすい。それに対して外来魚は伊豆沼の事例でわかるように、さまざまな方法を駆使して、いろいろな成長段階の対象を叩いていく必要があります。その中で、魚がいるのかいないのか、効いているのかいないのか、見ていくむずかしさもあります。最近は環境 DNAで、ある程度定量的なモニタリングが労力少なくできるようになりました。こういう手法をうまく併用することで、閉鎖水域ではある程度いないことを合理的に確認する方法が出てきたのかなと思いますが、まだ発展途上だと思います。
参加者 中島さんのご講演に関し、お聞きします。新規の外来生物が入ってきたとき、定着と未定着の識別をどうされていますか。見極めが非常にむずかしいと思います。しかし、最初の抑えは重要だと思うので、お考えを教えてください。また、ここ近年、増えてきている種が公開されているかどうか、教えていただけますか。
中島 たいへんむずかしいご質問ですね。今、特定外来生物は162種類ですが、これについてはホームページ上で定着、未定着を公開しています。
ただ、どこから定着と捉えるかは非常にむずかしいですが、基本的には有識者の先生方に相談しながら、環境省で決めているのが現状です。ですので、定着、未定着を環境省がどう考えているかについては、ホームページをご覧をいただけたらと思います。2点目の「増えている種が公開されているか」というのは、どのような種でしょうか。
参加者 公開されているならいいです。何年ぐらいで定着になるかが気になり、お尋ねしました。
中島 何年から定着したという情報はホームページには載せていないので、個別に知りたい種についてお問い合わせいただければと思います。お答えできる範囲でお答えさせていただきます。
細谷 ありがとうございます。
●企業による水辺の生きもの保全活動
 細谷
細谷 この20年には良い変化と悪い変化があったと思います。悪い変化については中井さんが整理してくれました。良い変化のひとつは、今日も講演がありました一般市民や企業の関わりが増えていることですね。SDGsなどもリンクして非常に積極的になっていると思います。そこで、企業からのお二人にお尋ねします。まず、NEC(株)の稲垣さんに、社員のモチベーションをどう高めているか、お尋ねしたいと思います。
稲垣(NEC(株)) 社員のモチベーションにも絡みますが、今企業がなぜ生物多様性や自然資本について取り組みを行っているかというと、気候変動もそうですが、企業の事業活動が環境に非常なインパクトが与えている中で、企業そのものだけではなく、サプライチェーン全体で(環境負荷を)見ないといけないという課題があります。CO
2も自社が出す分だけでなく、サプライチェーンが資源を採掘するところから、売ったものを使ったあとまで、どれだけCO
2を出すかが問われています。同じように、自然資本に関しても、サプライチェーンの上流からどんな影響を与えているのかを見て開示しなければなりません。それがTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)ですね。
つまり、それ(環境負荷)は企業のリスクにもなります。ですから、従業員のモチベーションになるかわかりませんが、これを従業員一人一人に理解してもらわないと、事業としてのリスクに対応できないところがあります。そこで、そのきっかけとして、身近な自然に触れてもらうという形でやってもらっています。我孫子事業場のイベントに来るのは30人40人ですが、NECグループ従業員5万人に対して活動の情報を共有することで、そういう活動が自分たちの事業にも関係してくるということを知ってもらう、そこを意識してやっているところがあると思っています。
細谷 ご発表を聞いて、隔離がいかに重要かも痛感しました。最大の敵はホモサピエンスです。私も近畿大学現職のとき、自衛隊の基地に希少種のカワバタモロコがいるのではないかと、地雷をよけながら調査したことがあります。希少種の保全に隔離は非常に重要と思います。
次は、三井住友海上火災保険(株)の深川さんにお伺いします。いろいろな保全活動をされていますが、海上火災保険会社がなぜこうした活動をされているのか、ちょっと読み取りにくいと思いました。
深川(三井住友海上火災保(株)) 私たちは金融保険事業ですので、たしかに淡水魚の保護や外来生物防除に直接的な関係はありません。しかし、私たちは河川の防災、減災の対策に直接関係しています。そのためにも、今の環境状況を認識することが重要と考えています。まずこういった活動から今の状況を知っていただく、伝える。それによって、自然が守られる、大きな災害の減災や防災につながる、と考えています。そのような意識を醸成していくことが非常に重要であり、そのための一環として、水辺の多様性を守る活動も重要と位置づけ、活動させていただいています。
細谷 ありがとうございます。企業の貢献がこの20年の中から芽生えていることをお話しいただきました。ぜひ、教育委員会などとも連携していただければと思います。
●地域づくりに貢献
 細谷
細谷 20年のいい変化の2番目は、地域づくりに対する貢献だと思います。冒頭に申し上げたように、外来種駆除と希少魚保護は表裏一体です。そして、希少魚を守ることも外来魚駆除も、地域づくりに非常に貢献していると思いました。和亀保護の会の西堀さんが強調されていましたが、対象種だけでなく、里地里山を守るところまで関わってくると思います。シナイモツゴ郷の会も地域と一体となったご活動をされておられますが、ご紹介いただけませんか?
高橋(シナイモツゴ郷の会) 私たちはNPOが中心になってシナイモツゴとゼニタナゴの保全活動をやっていますが、対象が農業者の管理するため池なので、農家、農業者と連携することが大事です。また、環境教育と後継者養成を考え、細谷さんがおっしゃるように小学生、高校生、大学生を対象に研修や里親活動を通して学んでもらうことを、重点事項として取り組んでいます。それによって、親御さんも理解を深めるという効果もあります。今後も進めていきたいと思っています。幸い、シナイモツゴとゼニタナゴは当会が申請し、大崎市教育委員会が天然記念物に指定してくれましたので、まさに教材として活用しながら、やらせていただければと思っています。
細谷 ありがとうございます。環境教育は主に若い人向けの活動ですが、私は西堀さんのお話で「駆除した個体の慰霊碑を作った」ということにも感銘を受けました。命を大事にする、動物愛護の問題もあり、お墓を作ることも地域との関係を深めるのではないかとと思います。
20年のいい変化に関連して、ひとつ用語をご記憶いただければと思います。それはウェル・ビーイングという言葉です。今日、経済的な充足があって、次のステップとして個人の権利や自己実現が保証され、身体的、精神的、社会的に良好な状態に持っていくことが、どの地方自治体も国家も求められています。ですから、この活動はまさに日本政府がやろうとしている、ウェルビーイングそのものに合致するのではないかと思っています。
●バス駆除釣りの催しは慎重に
 細谷
細谷 良い点をまとめてみましたが、次に、20年で悪くなった方で閉めたいと思います。中井さんと師田さんがかなり整理してくれました。バス釣り関係者の中には、「ブラックバスは行くところまで行っているから、もうこれ以上増えない」と言う人などもいますが、一つの場所において増えた減ったという問題ではなく、分布が今なお拡大している事実は、「拡げない」という外来法の趣旨に照らし合わせると大変問題です。オオクチバスも増えていますし、コクチバスはすごい速度で増えている。外来生物法が効いていないところだと思います。
その一方、ブラウントラウト、レイクトラウトなどは「産業管理外来種」にカテゴライズされていますが、こうした外来種を(容易に)逃げるようなところに置いていいのかということも課題です。また、密放流している現場を押さえなくても、(拡散している)現実があるということは、まさに高田会長がシンポジウムの冒頭で言われたように、私が缶を捨てたわけじゃないから缶蹴りして遊んで、また捨ててもいいんだ。これはまさに現在のブラックバス問題そのものじゃないかなと感じています。それが負の変化かと思いますが、コメントあるいはフォローありましたらお願いします。
参加者 昔は釣り入門の本に、「フナに始まりフナに終わる」と書いてありました。今は現実問題として、バスに始まりバスに終わるようになっている。だから、駆除釣りをうっかりやらないでほしいと思います。生まれて初めて釣った魚がバスだったら、バス釣り好きになりますよ。細谷さんに聞きたいのですが、優秀なバサーが入学してきたとき、そのバサーが初めて釣った魚は何だったんですか。
細谷 今の問題は非常に現実を表していますね。私にも突きつけられましたけど、日本の水辺の原風景が何から始まっているかということです。私は74歳なので、1960年以前の日本の水辺の原風景を熟知しています。それはタナゴ類でありフナでした。しかし、今はブラックバス、ブルーギルが原風景になっていて、それがどうして悪いのということになっている。むずかしいご指摘と思います。それを考えさせる意味でも、最初から(ブラックバスを釣ることは)認めるべきではないということですね。
西堀(和亀保護の会) できるだけ在来種を見せることが大事だと思います。私たちも現実的にはイシガメを見せたいけれど、イシガメの子ガメをたくさん用意できないし、アカミミガメも見せることになりますが、可能な限り在来種を見せるようにしたいと思っています。今後もできるだけそのようにやっていきたいと思います。
最近、たまたまアメリカザリガニもたくさんとったのでFacebookに載せたら、学校で使いたいから譲ってほしいというお申し出があり、丁重にお断りしました。アメリカザリガニは(現在、条件付き特定外来生物で)飼えるけれど、本来は飼うべきでないものを飼うことは教育の現場であってはならないと考えました。そういうことはどんどん縮小していくべきではないか、在来のものを見せる努力をするべきではないかと考えています。
細谷 具体的なお話をありがとうございます。ご質問の問題提起には必要十分なお答えにはなっていないと思いますが、これから考えていくということでお願いします。どうもありがとうございます。
中井 キャッチ&リリースについて補足させてください。キャッチ&リリースを外来生物法が関知しないのは、哺乳類、たとえばアライグマなどが間違ってワナにかかってしまったとき、特定外来生物だから殺さなきゃならないとさすがに困りますよね。つまり、錯誤や無知によって特定外来生物を一時的に生きたまま持ってしまった状態を救済する措置として、その場で放すことは OK としたんです。理屈としては、いるものをとってそのまますぐ放すから、プラスマイナスゼロで影響もない、という説明で了解したということです。それを、ブラックバスの特定外来生物指定に反対していたバス釣り関連のステークホルダーに対し、「これまでどおりキャッチ&リリースはできます」として、反対をなだめるようにも使われてきた経緯がありました。でも、バス釣りのキャッチ&リリースは錯誤でも無知でもないですよね。狙って釣って楽しんでいる。
また、釣りという行為では、魚が仕掛けにかかってからは釣具を通じて人と魚とが一体化している。つまり、所持しているのと似た状態になっている。このように、バス釣りにおける特定外来生物ブラックバスと人間との関わり方はだから、もっと考えを深めていくことが必要です。法的な問題も含めて。私は法律のことはわかりませんが、知恵を出し合い、このおかしな部分に対する解決策を見つけるため、お知恵をいただけたらと思います。
細谷 どうもありがとうございます。今日は私自身、非常に勉強になりました。いい意味でも悪い意味でも20年の間に大きな変化があったことが理解できました。これでディスカッションを終了します。
<終了後に提出された質問票とそれに対する回答(メールで送信)>

●
藤本泰文さんへの質問
「シンポジウム資料で、現在でもオオクチバスの違法放流が行われているとしているが、そう言われる根拠は何か?
外来生物法が施行されてからも検挙者はいない。根拠のない噂話であれば訂正してほしい」
●回答(
藤本さん)
違法放流と考えられる状況証拠は伊豆沼流域からも報告されています(※斉藤ほか2021)。違法放流は人目を避け、短時間で行うことが可能なため、現行犯で検挙するのは非常に困難です。したがって、検挙者がいないという事実だけをもって「違法放流が行われていない」と断定することはできません。
一方、淡水魚が水系を超えて、別の水系に移動することは通常困難です。日本には1級河川が108水系、2級河川は2000水系以上に存在します。こうした多数の水系による移動の制限があったため、日本には多様な淡水魚類相が形成されてきました。これは、日本列島ができ始めて以来の、およそ2500万年の長い年月をかけて築かれてきたものです。このような地形的特徴を持つ日本において、淡水魚のブラックバスがわずか数十年で国内に広く分布するようになった事実をどのようにお考えか、魚類学の研究者としてお尋ねしたいです。

※斉藤 憲治・三塚 牧夫・麻山 賢人・藤本 泰文. 2021. 宮城県伊豆沼・内沼集水域のため池で池干しによる駆除後に再び現れたオオクチバス
Micropterus salmoidesはどこから来たのか? 伊豆沼・内沼研究報告, 15: 107-120. https://doi.org/10.20745/izu.15.0_107
●
細谷和海さんへの質問
「キャッチ&リリースがブラックバス分布拡大の『負のスパイラル』としているが、キャッチ&リリース禁止地域でのバス釣りがされるのはひじょうに少なくなっている。釣りというブラックバスへの圧力が低いということになる。キャッチ&リリースのほうが魚に対して圧力がかかり、結果として魚が減ると思うがいかがでしょうか。また、釣り人が分布拡大に寄与しているとは言えないのではないか。外来生物法が施行されてから検挙者はおりません」
●回答(
細谷さん)
・「キャッチ&リリースのほうが魚に対して圧力がかかり、結果として魚が減る」における「魚」が何を指しているのか、判断がつきません。再度、詳しくご説明願います。
・「外来生物法が施行されてから検挙者はおりません」。確かに外来生物施行後のブラックバスの拡散には種々の要因が考えらえますが、密放流の現場を押さえるのは相当、困難でしょう。しかし、今更ながら河川水辺の国勢調査をはじめ魚類学関連のあまたの論文をご覧になればお分かりのように、ダム湖など自然拡散するはずもない水域においてバス釣りとリンクしている現実をどのようにお考えでしょうか? 具体的にご説明願います。